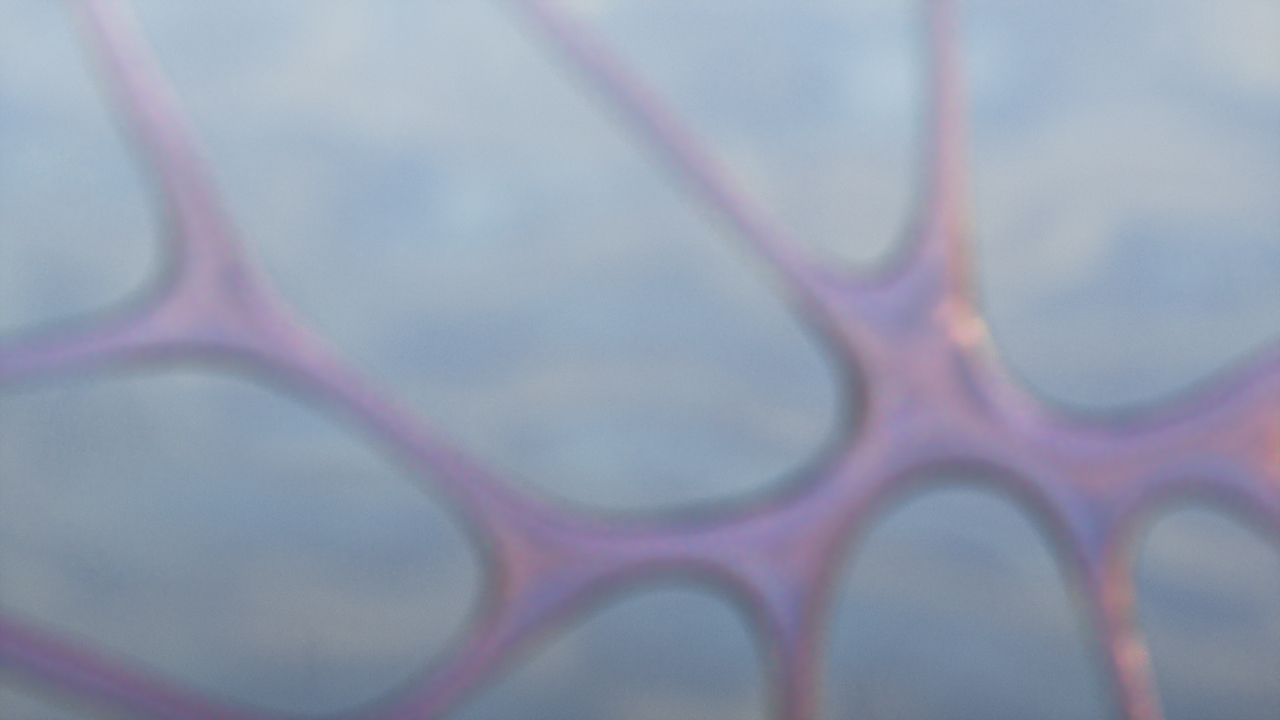RYOTO

RYOTO
Text:Yukako Yajima
Stylist: Kan Fuchigami
Stylist Assistant: Lisa Asai Sora Ashida Asa Kobayashi
Hair & Make Up: Katsuyoshi Kojima(TRON)(Ryoto/Natsuki)
Hair & Make Up: Riku Murata(AAAMYYY)
――5th アルバム『((ika))』(2024年5月リリース)が完成したとき、綾斗さんは「もっとやれた」「悔しさが残る」ということを口にされていたと思うんですけど、今回はどうですか? 私は、今のTempalayとしてやり抜いた感、探求し尽くした感のある音が完成していると感じたんですけど、綾斗さんの実感としてはどうですか。
そうですね。終わってみると「こうしておけばよかった」というのはありますけど、基本的に時間をかけて、これ以上ないくらいまで音を突き詰められたので、今のところは100点です。でも明日は98点になって、明後日は97点になって、っていうのはもう性ですね。
――その感覚こそが、一流のクリエイターとも言えますし。
100点を更新したら、多分やめますね。
――『((ika))』リリース後、昨年10月には武道館ライブがあり、レコード会社がワーナーからSPACE SHOWER MUSICへ戻ってきたという変化もありました。武道館以降の10か月は、Tempalayとしてどういうことを考えて、どういうことを大事にしていた期間だったと言えますか。
「どういうふうに次のタームへ移っていくか」みたいな感覚はあったんですけど、かといって抽象的で。武道館以降、特に日本で「大きなところでやりたい」「東京ドームを埋めたい」みたいなテンションではないので、これからどう転がっていくのだろうっていう状態でレコーディングに入って。Tempalay Houseという企画で、1ヶ月間部屋を貸し切ってみんなで作っていく中でこういう音作りができて、そこで世界がチラついてきた感覚はあります。今は、ワールドワイドというより、ヨーロッパで賞を取りたいなというマインドになっていますね。
――武道館が終わって、「次は海外を目指そうよ」という話になってこの音を作ったというよりかは、この作品を作りながらその手応えを感じられたということだったんですね。
そうです、勝てそうだなというか。とにかく肌感ですね。
――そこから新作を作るにあたって、今日取材をさせてもらっているこの場所を1か月間貸し切って、全部の機材を持ち込んで、1か月かけて制作したんですよね。ここ、普段はレンタルスペースなんですか?
もともとは家具屋さんなんですけど、今は普通のレンタルスペースで、ここにドラムや卓と、向こうの部屋にシンセをぶち込んで。ぎゅうぎゅうなんですけど、ここにいろんな人が来訪して、ついでに音を録ってみたいな、遊びながらやっていた感じですね。立地が最高じゃないですか。しかも気分もよくて。前のパン屋とかLittle Nap(コーヒースタンド)へ行って、普段コーヒーなんて飲まないのに買ったり、Little Napのオーナーさんにギターやアンプを借りたり。夜はここで宴会をしたり、そういうことを全部包括してよかったです。
――そういう作り方をしたいと思ったのは、綾斗さんの中で何を求めていたからですか。
The Flaming Lipsの『Yoshimi Battles the Pink Robots』というアルバムの音が前衛的で、どうやらこういう手法で録っているということをエンジニアの奥田(泰次)さんが調べてきて、それはたしかに楽しそうだなと。でもいい場所があまりないんですよ。ここも音が響くし、車も通るし、劣悪っちゃ劣悪なので。そういうのもありきで録ったのでThe Flaming Lipsとはまたちょっと違う質感になっているんですけど。大滝詠一さんが家を借りてやっていたレコーディング方法とか、カメラをつけて常に監視されているような状況でそれも込みで録っていくとか、そういうことをやってみたかったという感じですね。

――実際、ここに機材を持ち込んで毎日通いながら作って、しかもYouTubeでその様子を配信して、という手法を取ってみたことで、どういう音楽を作れた実感がありますか?
やり方次第では、めちゃくちゃいいスタジオで録るのとあまり変わらないなと思いました。日本はあまりにも「おぼっちゃま音楽業界」というか、特に売れれば売れるほどいい環境でいいエンジニアがいるゆえに創造性を欠いていくような気がする。向こうの人たちはこういう場所を常に持っているわけなので、本当はめちゃくちゃ自然な状況である気がしますね。
――いい音とは何か、という話でもありますよね。設備が整ったスタジオで綺麗な音を完璧に録るものも「いい音」だけど、綾斗さんは違う意味での「いい音」を求めていたということなのかなと。
音というよりは、その過程とかのほうが大事かなと思います。今日と明日では細胞があまりにも入れ替わっていて感じ方が違うので、毎日「やっぱりこうしていこう」ということを繰り返せたのがよかったですね。
――具体的に曲に触れながら聞かせていただくと――そもそも、今回は作曲に3人の名前がクレジットされていますけど、曲の作り方自体これまでと変えたんですか?
作り方は変わってないですね。デモ出しの時点で割と完成形に近いものを出すんですよ。それを各々好きなように料理するというのが基本ですね。ポスプロを増やして、最終的に音をみんなで詰めていくという作業はやりましたけど。
――読者に「ポスプロ(ポストプロダクション)」とは何かを伝えると――。
録り終えた音を、もう一度、いろんな機材を使ってアップデートしていく作業ですね。それをやったのは、そもそも「The Flaming Lipsはどうやってこの音像を作ったのだろう」というところから入って、自分の中で目指したい音像があったからで。結局、どこかのスタジオを借りて1日でやりきるというのは、その場のグルーヴでしかなくて。音を持って帰れたことがデカいです。やっぱり音を外に持っていくのが超大事だと思っているんです。それを僕は「音を歩かす」って言っているんですけど。一回外に連れていって、雑音の中で聴くことで違う感覚を得られたりするんですよ。その曲が導かれていく感覚を持てるというか。だからレコーディングの工程は一緒でも、環境と期間で音が変わるなと思いました。
――曲が導いてくれる音を精査して、それを突き詰める余裕を持てること自体が、綾斗さんにとっては大事だったんですね。
いや、僕はめっちゃめんどくさがりなのでやりたくないんですけど。基本的に「これでいい」って感じ。でも3人集まると意見が全然違うので、それがよかったですね。みんなが意見を言える環境を作れたということが大きいんじゃないですかね。録り直しがきくことも大きかったです。心の余裕が全然違いますね。チャレンジできるじゃないですか。「これがしっくりこなくても明日しっくりくるかもしれんし、しっくりこなかったら別のものを録れるし」っていう、それができたことがデカいです。

――それができたことが「やりきった」と思える気持ちにつながっていそうですね。
うん、そうですね。本来、常にこういう場所があるべきですよね。
――1曲目“Magic”はメルボルン滞在中に書き始めた曲だそうですね。そもそもなんでメルボルンに行かれたんですか?
武道館が終わって、それまでめちゃくちゃ忙しかったのでちょっと休暇がほしいなと思って。友達がメルボルンで暮らしているので、そこに訪れたというだけなんですけど。「メルボルンにすごく感銘を受けて」みたいな話というよりは、シンプルな備忘録ですね。曲を作れたらいいなと思いながら行った中で、ギターで骨組みを30分くらいで作った曲です。
――備忘録といってこれができあがってくるのが、綾斗節ですね。
本当ですか。やっぱり向こうで作ったことがデカいと思います。これは脳科学的に証明できるものがあるらしいんですけど、環境や国によってクリエイティブのテンションが変わるらしくて。久石譲がヨーロッパで感銘を受けて、めちゃくちゃ頭が回転してたくさん曲を作って、同じ楽団を日本に呼んだけど、ダメだったという話があって。日本って湿度も高いし、鬱屈としていて、人も暗いし――それが別に悪いわけじゃないですけど――音楽って、作る場所や録音する場所で左右されるなとは思いました。
――私はメルボルンに行ったことがないんですけど、多文化が溶け込んだ都市だと言いますよね。この曲もいろんな文化の要素が詰め込まれたアレンジだと思うのですが、そこをつなげて語るのは安直すぎる?
移民の町なので、ヨーロッパ的な雰囲気があったり、ニューヨークみたいな雰囲気があったり、大きな公園がバーってあったり。昼は暑くて、夜は寒いんです。でも日中も風が吹くと風が冷たいんですよ。「なんで冷たいの?」って聞いたら、南極の風がそのまま運ばれてくるらしいんです。そういうところに感化されたかもしれないです。あと、メルボルンで録った音がめっちゃ入ってます。
――メルボルンには何日くらいいらっしゃったんですか?
1ヶ月いる予定でしたけど、10日で帰ってきました。向いてないんだと思います(笑)。
――向いてない?
長期滞在が向いてないと思います。
――飽きて帰ってきた、みたいなこと?
飽きたというか、普通に寂しくなって……ははははは(笑)。

――(笑)。2曲目の“かみんち”は――音楽の起源は霊や神に近づく行為だと捉えられていますけど、それを感じさせてくれる曲で。
久高島へ行ったとき、スピリチュアルな体験をしたんですよ。先祖崇拝で、基本的に女性が一番崇められていて、「神の人」という意味で、女性の地域の祭祀を担う女性を「かみんちゅ」って言うんですけど。「かみんちゅ」だとちょっと宗教的だなと思って“かみんち”にしました。
――どういう体験をしてきたんですか?
それはあまり話さないほうがいいと思うんですけど……端的に言うと、人は何を神と感じるのかということを体験した感じですね。見える見えない、感じる感じないとかって、めちゃくちゃ現実的に起こり得る事象なんだなって。
――“かみんち”はTempalayの突き詰めたネクストステージ感を示している曲で、これを先行配信シングルとして選んだこともかっこいいなと思いました。
売れなさそうですよね(笑)。普通にかっけえなと思ったから出しただけなんですけど。感覚的な体験をしてほしいなと思って作りましたね。所詮「音」なので。どうやったら音でアトラクション的な体験ができるかな、というアプローチが“かみんち”ですね。
――EPでは“かみんち”のあとに“動物界”が続くわけですけど――多国籍、霊界、自然界、動物界、宇宙、そして人間界、それらすべてがないまぜになっていて、グニャリとしているような世界観を、「これぞTempalayが映し出す現実だ」というふうに見せてくれるのが『Naked 4 Satan』だと思いました。それはこれまでもやっていたTempalayならではの表現だと思うんですけど、それがネクストレベルの濃さに更新されていますよね。
いやでも本当、備忘録なので。“動物界”も、たまたま向こうで知り合った人にメルボルンのグレート・オーシャン・ロードという断崖絶壁の道沿いを連れていってもらって、いろんな野生の動物を見て、っていう感じですね。たまたま『動物界』というフランスの映画がやっていて、それらを自分の中でぐちゃっとしました。
――トロピカルなアレンジから、サビ終わりで展開が変わっていくのは、綾斗さんの中でどういうイメージがあったんですか?
感覚として、「こっち側」と「向こう側」というのがあって。
――「人間」と「動物」?
そう、あと「自然」とか。僕らって「自然が美しい」とか言うけど、多分7色しか見てなくて、その奥はとても凄まじく、魑魅魍魎としていて、パワーもすごくて。間奏に関しては、そこに「お邪魔します」みたいなノリでしたね。そこにグーッと入っていって、自分たちの知らない本当の営みとか、そういうものがぱっと開けるみたいなイメージで作りました。
――自然溢れる場所に行くと私たちは「空気が美味しいね」「美しいね」とか簡単に言ったりするけど、実際には自然の恐ろしさや脅威というものがあるし。
そうそう。でもみんな虫嫌いだし、熊は怖いじゃないですか。みんな本当の自然を知らないと思って。僕が知っているという意味ではなく、そういう距離感を持った曲ということですね。
――最後の“Bye”は、“Magic”と同じ始まりだったりして、他3曲で得たものを混ぜ合わせた曲という感じもしていました。
Tempalay Houseという場を反映させた曲を作りたかったんです。ギターも扉を開いて録ったり、ここの空気感を閉じ込めた曲が“Bye”ですね。メルボルンで出会った人たちの声のサンプリングと、ここの空気感を混ぜるという意図がありました。

――最初からAAAMYYYさんが歌うものとして書き始めたんですか?
たしかそうです。自分が歌って恥ずかしいものにAAAMYYYに歌わせるというギミックです。
――(笑)。何が恥ずかしいんですか。
なんて言うんですか……監督が出演しちゃうみたいなサムさになる感じがあって。あとはEPのバランスとしてAAAMYYYが歌ってる曲があっていいかなっていう。そんなに深い意味はないですね。別にその辺の女の子でもよかったですし。
――それはよくないでしょう(笑)。
“かみんち”の〈ヤーヤーヤー〉も一般の方が歌っているので全然ありだと思うんですけど。究極を言えば、ドラムを叩いたりピアノやギターを弾いたりする人が違ってもいいと思うんです。アイドルじゃないから。過程とか根底のほうが大事ですね。抽象的ですけど、別のものが入ることで空気感がミックスされると思うんですよ。音楽って自己満なので「バンドだからバンドでやりたい」みたいなこだわりもわかるんですけど、それは狭いなと思います。
――そうやってできあがった4曲入りEPに『Naked 4 Satan』というタイトルをつけたのは、どういう理由からですか?
これ、全然意味はなくて。メルボルンにあるバーの名前なんですよ。「Naked for Satan」という、僕が毎日通っていたバーがあって。4曲入りなので「4」にしただけです。かなりクレイジーなバーなんですけど、居心地のいい場所ですよ。ぜひ行ってほしいです。
――今後も、今回のような作り方をやっていきたいですか?
やっているときは「絶対にやりたくないな」と思っていたんですけど、やっぱりめちゃくちゃいい環境だったなと思います。ここじゃなくても、1、2ヶ月場所を借りてやるのはいいと思います。これからもボスプロはやっていくと思いますね。
――綾斗さん的に「もうやりたくない」と一瞬でも思った、大変だった部分はどういうところですか?
録り方ですよね。車の騒音もそうですし、モニターがないので大きい声で指示を出すしかないし。いい環境に慣れちゃっている部分もあるので、よろしくないですね。それこそ不自由なところからバイタリティが生まれることもあると思うので。ここで録れるんだったら、どこでも録れるなとは思いました。だから、たとえばテーマを決めて、それに合ったレコーディング環境を考えるのもありかなと思います。

――今後海外への気持ちが強くなっている中で、そのためにやりたい、やるべきだと思っているのはどういうことですか。
一番は音だと思います。世界の音のトレンドは変わるけど、それを日本はあまりにも無視しているなと思う。なのでそれをちゃんと把握して、その半歩先は何なんだろうという考え方をしていくんじゃないですかね。別に世界が偉いわけじゃないので、僕らが圧倒的なものを作ればいいだけだと思っているんですけど。
――Tempalayとは何なのか、強烈な個性とは、というところが今作ではネクストレベルにいっていると言えるくらい研ぎ澄まされたと思ったので、そのままグローバルに届いてほしいなと思います。
ありがとうございます。毎回そう言われたいですね。
――進化し続けたいと。
進化も退化もどちらも。退化も大事じゃないですか。現状維持が一番やばいと思う。かっけえものを作るってことです。
――ここまでで、リスナーに言い足りてないことは何かありますか?
一聴して気づかないものがたくさんあると思うので、いろんな場所に連れていってあげてほしいなと思います。季節、温度感、湿度とかでも音楽の聴こえ方は変わるので、いろんな環境に連れていってあげてほしいですね。それこそ、何の機器で聴くかでも変わりますよね。いろんなところで味わうにはちょうどいいサイズ感のEPだと思うので、可愛がってあげてほしいなと思います。

インタビューの様子がMOVIEでも見れます。
※Tempalay the planktonメンバー限定になります